
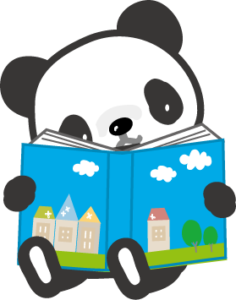
・自分のノートが誰かの役に立つのが嬉しい
・人のノートを見て勉強したい
・分からない問題をみんなで教え合いたい
Contents
Clearとは
- ノート共有
生徒が自分で作ったノートの写真をアプリ上に公開することです。現在30万冊以上のノートがClear上に蓄積されています。 - Q&A
アプリ上で生徒が自由に質問できます。また上がっている質問に対しては、登録している生徒が回答していきます。
Clearの3つの特徴
「ノート共有」で見る側も作る側にも学習効果

いつでも悩みを解決できる「Q&A機能」
SNS要素でモチベーションアップ
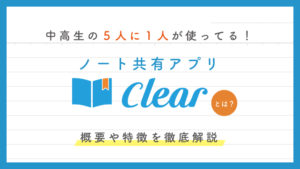
アプリ開発者の新井さんから保護者へメッセージ
Clearには生徒の能動的に学ぶ姿勢も身に付けてほしいという思いも込めています。
学校の授業は基本的に受動的になりがちですが、社会に出てから必要になるのは能動的な学習姿勢です。
これを身に付けるには堅苦しい場所ではなく、楽しいコミュニティーでやるのが重要たと私は考えています。
だからそういった点も期待して生徒さんに使っていただきたいです。
またClearは保護者の方にも使ってほしいサービスです。
中学生の娘と一緒にClear使ってノートを投稿し、カリスマノート作家になった現役のお母さんもいます。
現在200冊以上ものノートを公開していて、フォロワーの数も5000人越えです。
なので是非、保護者の方にも一度Clearを肌で感じみてほしいと思っています

こんなこともできます・番外編
シールを張り付けてみよう
アプリ上でも、紙のノートのように付箋やシールを貼る機能が使えます。
マーカーのように線が引けるシールもあるので、自分の好きなレイアウトに変えられるのも楽しいポイントです。
イラスト入りノートを作ってみよう
人気のノートの中には、イラストが盛り込まれてるものも多いです。
暗記が嫌い!という人でも苦手意識なく勉強できるかもしれません。アプリに慣れてきたら、自分でもイラスト入りのノ
ートを作って公開してみませんか?
まとめ











